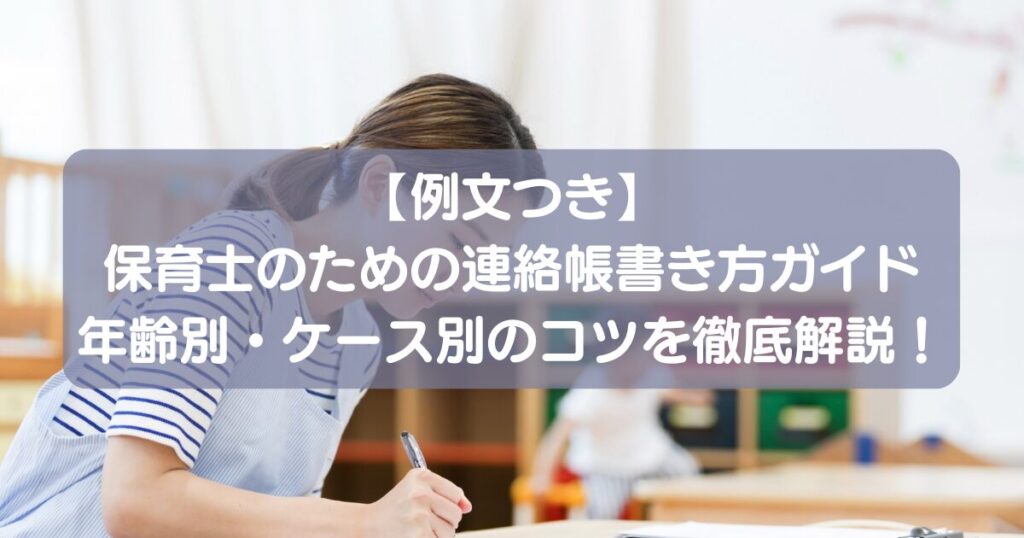保育士として毎日欠かせない「連絡帳」
子どもの園での様子を伝える大切なツールですが、「今日は何を書こう…」と悩むこともありますよね。
保護者の目にどう映るかを考えると、慎重になってしまうのも自然なこと。
この記事では、保育士歴12年の私が連絡帳を書く際に押さえておきたい基本や、年齢別・シーン別の書き方のコツ、すぐに使える例文をご紹介します。
日々の記録が保護者との信頼関係を深め、子ども一人ひとりの成長を見守る大切な手がかりとなるはずです。
書くことに迷った時こそ、ぜひ参考にしてください。
保育士が連絡帳を書く目的と心構え
保育士さんからの連絡帳楽しみにしています!
毎日の子どもの様子がわかる連絡帳は保護者にとって大切なものですよね。
ここでは、保育士が連絡帳を書く目的と心構えを解説します!
連絡帳は、単なる日々の記録ではありません。
保育士と保護者が「子どもを一緒に見守るパートナー」であることを実感できる、大切なコミュニケーションツールです。
連絡帳の目的とは?
1.子どもの様子を共有するため
園での活動内容や子どもの姿を伝えることで、保護者は子どもの成長や変化を実感できます。
2.家庭と園をつなぐ橋渡し
ご家庭での体調や生活の変化を知ることで、保育でも無理なく対応できます。
3.安心して預けられる関係を築くため
丁寧なやり取りを重ねることで、保護者からの信頼を得ることができます。
書くときに意識したい心構え
1.読んでほっとする言葉を心がける
例えば「笑顔がたくさん見られました」「好きな遊びに夢中になっていました」など、ポジティブな表現を意識しましょう。
2.「何を書くか」より「どう伝えるか」
事実を並べるだけでなく、保育士自身の視点や気づきを一言添えるだけで、ぐっとあたたかい文章になります。
3.報告ではなく対話を意識する
連絡帳は一方的な記録ではなく、保護者とのやり取りの場です。
保護者の記載にも目を通し、共感や返信ができると関係性が深まります。
連絡帳記入の基本マナーと避けるべき表現
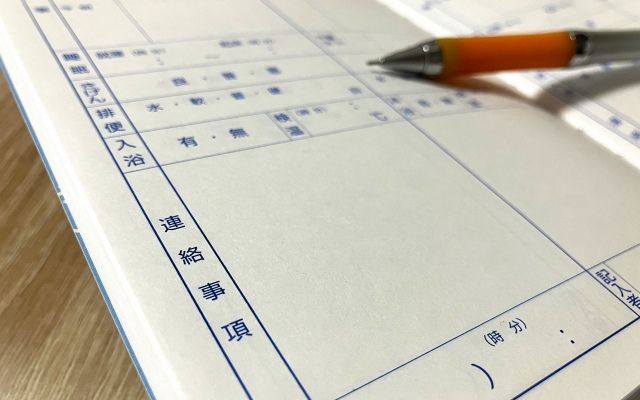
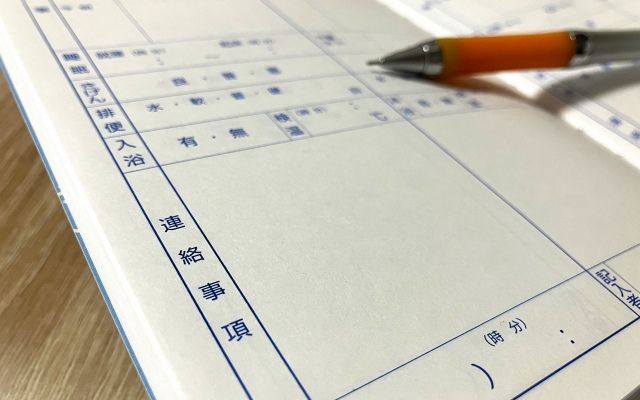
どんなに内容が素晴らしくても、誤字脱字や冷たい印象の表現では、保護者の心には届きません。
ここでは、連絡帳を書く上で守りたい基本マナーと、避けたほうがよい表現について解説します。
連絡帳記入の基本マナー
1.丁寧な字・誤字脱字のチェックは必須
紙媒体の場合は読みやすい文字で、紙でもアプリでも誤字脱字に注意しましょう。
丁寧さは保育士の印象を左右する大事な要素です。
2.敬語や言葉づかいに配慮する
「~してあげました」「やってます」などの話し言葉は避け、丁寧で柔らかい表現を心がけましょう。
3.適度なボリュームで伝える
短すぎると情報が足りず、長すぎると読み手が負担に感じることも。
簡潔かつ具体的に書くのが理想です。
避けるべきNG表現とその理由
こんな表現していませんか?
保護者の受け取り方を大きく左右するため、ネガティブな表現は極力避けましょう!
| NGな書き方 | なぜNG? | 替わりの表現例 |
|---|---|---|
| 「今日はずっと機嫌が悪かった」 | 否定的な印象を与えやすい | 「今日は眠気が強く、落ち着かない時間が多かったですが、お気に入りの絵本の時間には笑顔が見られました」 |
| 「片付けをしませんでした」 | 子どもを責めているように感じられる | 「まだ遊びたい気持ちが強かったようで、片付けに少し時間がかかりました」 |
| 「言うことを聞きませんでした」 | 命令口調に感じられる | 「自分の意思をしっかり伝える姿が見られました」 |
連絡帳は、「保護者が安心して子どもを預けられる園かどうか」を判断する材料でもあります。
ネガティブな表現には特に気をつけ、文字ではうまく伝わらない場合、気になる点はニュアンスや表情ありきの口頭で伝えるのがベストです。
年齢別|発達に応じた連絡帳の書き方と例文


子どもの成長段階に応じて、連絡帳に書くべきポイントも変わってきます。
ここでは年齢ごとに、どんなことを観察・記録し、どう書けば伝わりやすいかを例文つきで解説します。
0歳児|「はじめて」を一緒に喜ぶ
書き方のポイント
- 体調、生活リズム、排泄など基本的な様子を丁寧に記録
- 「はじめてできたこと」や「興味を持ったもの」は特に詳しく
- 言葉にならない感情や表情を伝えるのがコツ
例文1:日常の様子
「今日は午前中のお散歩で風に揺れる葉っぱをじーっと見つめていました。手を伸ばして触れようとする姿がとても可愛らしく、自然に興味を持ち始めている様子が見られました。」
例文2:成長の記録
「今日はつかまり立ちに挑戦!テーブルの縁に手をかけて、何度も立ち上がろうとしていました。何度か成功してとても嬉しそうな笑顔を見せてくれましたよ。」
1~2歳児|「自己主張」や「言葉」の芽生えを伝える
書き方のポイント
- 言葉やしぐさのやりとりを記録
- イヤイヤ期の行動は自己表現として捉える
- 感情の動きを丁寧に描写
例文1:遊びの中での成長
「今日は粘土遊びをしました。○○くんは丸めた粘土をおにぎり!と見立てて保育士に『どーぞ!』と渡してくれました。やり取りの遊びがどんどん豊かになっています。」
例文2:感情の表現
「お片付けの時間に『まだ遊びたい!』と主張する場面がありました。気持ちを受け止めたうえで声をかけると、納得しておもちゃを箱に入れてくれました。自分の気持ちを表現できるようになってきたこと、成長を感じます。」
3歳児以上|「人との関わり」や「挑戦する姿勢」を伝える
書き方のポイント
- 自主性や周囲とのかかわり方を具体的に
- 新しくできるようになったことは丁寧に描写
- トラブルの描写は避け、前向きな言葉で成長を伝える
例文1:友達とのかかわり
「今日は積み木遊びを通じてお友達と一緒にお家を作っていました。『ここにドアつけようよ!』と提案したり、お友達のアイデアにうなずいたりする姿に、協調性の芽生えを感じました。」
例文2:挑戦と成長
「園庭の鉄棒に一人でぶら下がることに挑戦しました!『先生、見てて!』と声をかけてくれて、一度も手を離さずに10秒もぶら下がれました。自信に満ちた笑顔がとても印象的でした。」
ただし、3歳以上になるとクラス全体の活動の様子を伝えるようになることが多いです。
これは、少しずつ自分の言葉で親に「今日あった出来事」や「自分の気持ち」を伝えられるようになっていくからです。
とは言っても、まだまだうまく伝えられない子どもも多い年齢。個別の成長や様子などは、送迎時に伝えると親子のコミュニケーションのきっかけづくりになりますよ。
シーン別|伝わる連絡帳の書き方と例文


日々の保育には、成長や関わりが色濃く表れるさまざまなシーンがあります。
ここでは、特によくあるシーンごとに、どんな視点で観察し、どう文章にまとめると伝わりやすいのかを具体的に解説します。
登園初日|保護者の不安をやわらげる
書き方のポイント
- 簡単な自己紹介を添える
- 泣いた、戸惑ったなどの姿も「適応の一歩」として伝える
- ポジティブに締めくくる
例文1(泣いていた場合)
「担任の○○です。1年間よろしくお願いいたします。今朝は初めての登園で少し泣く姿も見られましたが、大好きなおもちゃを見つけると興味を持ち、徐々に気持ちも落ち着いてきました。保育士と一緒にブロック遊びをしながら笑顔も見られました!」
例文2(緊張していた場合)
「朝は少し緊張している様子でしたが、慣れたお友達が声をかけてくれたことで表情が和らぎ、自分から近づいて一緒に遊ぶことができていました。これから少しずつ園の生活に慣れていけるよう見守っていきますね。」
遊んでいる様子|子どもの興味や関わりを伝える
書き方のポイント
- 遊びの道具や仲間とのやりとりを描写
- 成長、発達が垣間見える部分に注目
- 季節や流行の遊びも積極的に取り入れる
例文1(1歳児)
「今日は風船遊びをしました。○○ちゃんはふわふわと動く風船を目で追いながら、手を伸ばして『キャッキャッ!』と声を上げて喜んでいました。色や動きに強く反応している様子がとても印象的でした。」
例文2(3歳児)
「園庭で虫探しに夢中でした。今日はテントウムシを見つけて、『赤いのがいたよー!』と大興奮。保育士に図鑑を持ってきて見せてくれ、『これはナナホシテントウかな?』と調べている姿に、探求心の芽生えを感じました。」
保護者からのコメント・相談への返信
書き方のポイント
- 否定せず受け止める
- 家庭との連携を意識した言葉を選ぶ
- 園での様子と合わせて安心感を届ける
例文1(食事についての相談)
「お家で食が進まないとのことですが、園では落ち着いた雰囲気の中でしっかりと食べられていますよ。スプーンの持ち方も上手になっていて、完食することも増えてきました。園での食事量の調整が必要な場合はお声かけくださいね。今後も様子を見守っていきたいと思います。」
例文2(夜泣きについて)
「夜泣きが続いているとのこと、お母様(お父様)も大変ですね。園では午前中しっかり活動し、お昼寝もぐっすり眠れています。疲れが出ている可能性もあるので、無理のないリズムで過ごせるよう園でも気をつけて見ていきます。」
アプリ時代の連絡帳記入のコツ


近年、紙の連絡帳からアプリへの移行が進んでいます。
便利な一方で、「事務的に見えないか不安」「定型文ばかりになってしまう」という声も。
ここでは、アプリ記入ならではのポイントと注意点を紹介します。
アプリでも「あたたかさ」は伝えられる
アプリではテンプレート項目(体温・食事・排便など)が自動記録されることも多いため、「コメント欄」や「自由記述欄」が保護者との信頼関係をつくるカギになります。
例文1(0歳児・日常)
「朝は少し眠たそうにしていた〇〇ちゃん。お気に入りの音の鳴るおもちゃで笑顔が見られました。音が鳴るたびに目を丸くしてあっ!と反応する姿がとても可愛らしかったです。」
例文2(2歳児・返信)
「おうちでの着替えを嫌がっているんですね。園では『自分で!』とズボンを履こうと頑張る姿がみられます。園では、着脱を少し手伝うとうまく着られた!と自信につながっているようです。お家でもちょっとだけサポートをぜひ試してみてください。」
スマホ入力でも気をつけたい3つのこと
1.文章を短く区切る
長い文章は読みづらくなるため、1~2文で区切ると印象が柔らかくなります。
2.絵文字や記号の使い方に注意
園の方針にもよりますが、ハートやキラキラ絵文字は使いすぎると不安に感じる保護者もいます。
顔文字や句読点など、落ち着いた表現がベター。
3.コピー&ペーストの差別化
クラス全体に同じ活動をしていても、1人ずつの「個別コメント」を1行でも添えることで、ちゃんと見てくれているという印象になります。
忙しい時の簡潔だけど丁寧な文例集
「今日はお友達と協力してブロック遊びに取り組んでいました」
「外遊びでは砂場でケーキ屋さんごっこを楽しんでいました」
「午睡後はまだ眠たそうにする様子もありましたが、おやつの時間には元気に復活していました」
アプリになっても、連絡帳の本質は変わりません。
「どんなふうに過ごしていたか」が保護者に届くよう、気持ちを込めて一言を添えることが大切です。
書くことがない…と感じた時ヒント集


「今日は特に変わったことがなかった」「何を書けばいいのか浮かばない」—そんな日もありますよね。
ですが、何もないという日は、実は安定していた日。
少し視点を変えれば、連絡帳に書けることは意外と見つかるものです。
視点を変えれば「書けること」はある!
1.いつも通りこそ、安心を伝えるチャンス
例文:「今日はいつも通り元気いっぱいな〇〇くんでしたが、おやつの後に大好きな絵本を読んでいる時の落ち着いた表情が印象的でした。」
2.小さな変化も立派な成長記録
例文:「お昼寝前、自分から布団に入って目を閉じようとしていました。ルーティンがしっかり身についてきているようです。」
観察キーワードで視点を増やそう
書くことに迷ったときは、下のキーワードをヒントに「子どもの姿」を振り返ってみましょう。
| 視点カテゴリ | キーワード例 |
|---|---|
| 身体の動き | 歩き方、階段の上り下り、ジャンプ、スプーンの使い方 |
| 言葉 | 新しく話した言葉、話しかけ方、歌のフレーズ |
| 感情の動き | 嬉しそうな場面、怒った理由、泣いたきっかけ |
| 人との関わり | 友達とのやりとり、声かけ、順番を待てた場面 |
| 遊びの集中度 | どれくらい集中していたか、何に夢中だったか |
「書かないといけない」から「伝えたい」に変える
連絡帳は毎日完璧に書かないといけないものではありません。
少しの気づきや子どもらしい姿を一言添えるだけでも、保護者にとっては十分な安心材料になります。
「今日はお昼寝がぐっすりでした」「おかわりをして満足そうでした」
そんな短い一文が、保護者の心をふっと軽くすることもあるのです。
まとめ
保育士にとって連絡帳は、単なる報告のための業務ではありません。
それは、子ども一人ひとりと丁寧に向き合い、日々の小さな成長や思いを保護者に「見える形」で届ける大切なコミュニケーションツールです。
書くときに迷ったら、「私は今日、この子のどんな姿を見たのか?」「それをどう感じたのか?」という自分のまなざしを思い出してください。
たとえ短い文章でも、あなたの気づきや想いが込められていれば、それはきっと保護者の安心や信頼につながります。
毎日が忙しい中でも、子どもの一瞬一瞬をすくい取って、やさしい言葉で保護者へ届ける。
そんな連絡帳を、明日から少し肩の力を抜いて、あなたらしく書いてみてくださいね。