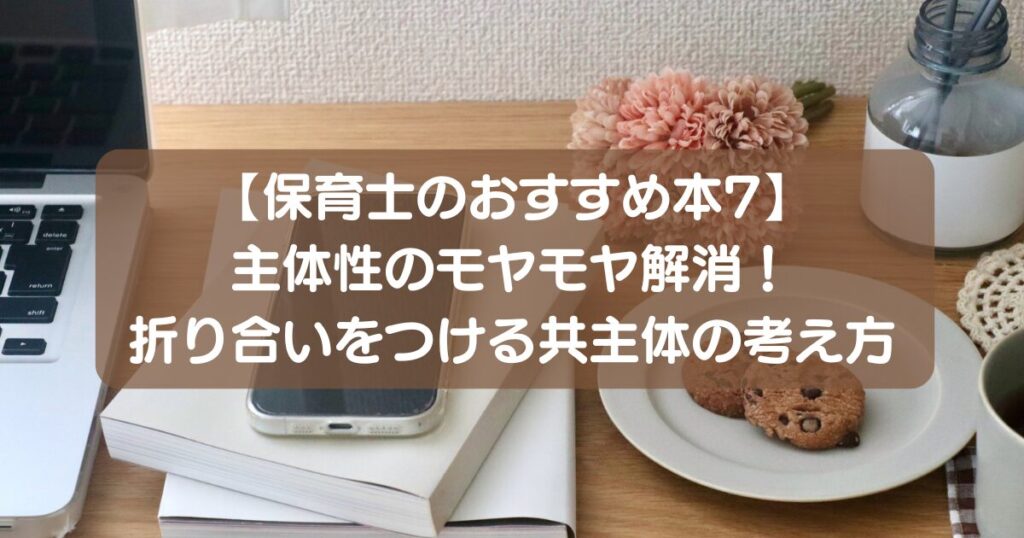「うちの園でも主体的な保育って言われるけど、正直よくわからない…」
「自由保育と一斉保育、結局どっちが子どもにとっていいんだろう?」
保育の現場で主体性という言葉を頻繁に耳にするようになり、理想と現実のギャップに悩んでいませんか?
子どもの主体性を尊重したい気持ちはあるけれど、具体的にどんな関わり方をすればいいのか、迷ってしまう保育士さんは少なくありません。
この記事では、大豆生田啓友氏監修、おおえだけいこ氏著の『子どもが中心の「共主体」の保育へ』を参考に、あなたのモヤモヤを解消する新しい概念「共主体(きょうしゅたい)」をご紹介します。
これは、子どもと大人の主体性に折り合いをつけ、両方の良いところを活かし、子どもと大人が共に育ち合う保育のヒントが詰まった一冊です。
ぜひ、これからの保育の参考にしてください。
主体性のモヤモヤを解消!新しいキーワードは共主体
この本は、読者が抱える「主体性って何?」という素朴な疑問に対し、コミック形式(約40ページ)も交えて非常にわかりやすく解説してくれます。
主体性とは違う?共主体とは?
この本の核となる概念が共主体です。
これは、子どもの主体性と保育者性の主体がバランスよく共存し、お互いの主体性を尊重しながら学び合う関係を意味します。
一方的な見守りや指導ではなく、子どもと大人が相手の主体性と折り合いをつけるという、これからの保育に欠かせない視点を提供してくれます。
自由保育 vs 一斉保育ではない!
読者の悩みに直結する自由保育と一斉保育の対立についても、この本は明快な答えを出しています。
A(自由保育、見守り)かB(一斉保育、指導)かではなく、A & B(両方のバランス)でいくべきだと提案します。
この考え方を知ることで、「どちらかに決めなければ」という重圧から解放され、柔軟な保育デザインができるようになります。
領域ごとの具体的な実践ヒント
理論だけでなく、日々の実践に落とし込むための知恵が豊富です。
この本の第3部では、自然環境教育・音楽教育・身体活動・表現活動など、領域別に専門家による理論と、理論内容を実践している園の事例が、写真やイラストとともに具体的に紹介されています。
【実践編】共主体を叶えるハイブリッドな関わり方

共主体の考え方を現場でどう活かすか。
自由保育と一斉保育の良さを取り入れ、子どもの主体性を引き出すためのヒントをご紹介します。
子どもの最善の利益を上位概念とする
子どもと大人の主体がぶつかったとき(例えば、自由遊びの最中に一斉に片付けたいときなど)、どちらを優先すべきか迷うことがあります。
【判断基準を持つ】
どちらの主体を優先すべきか迷ったら、子どもの最善の利益という上位概念を思い出しましょう。
この視点を持つことで、「今、この子にとって本当に必要なことは何か?」という見方から、一斉保育的な関わり(指導)が必要なのか、自由保育的な関わり(見守り)が必要なのかを判断する軸ができます。
対立ではなくバランスで考える
一斉保育と自由保育を敵対させるのではなく、子どもの活動を中心にバランスを意識して保育を組み立ててみましょう。
【計画に幅を持たせる】
「今日は必ず〇〇をする」とカッチリ決めるのではなく、「〇〇の時間も取るが、その後は子どもの興味に合わせて活動を広げる」というように、柔軟な時間設定を取り入れます。
これにより、大人の指導と子どもの探求がスムーズにつながります。
領域の実践事例からヒントを得る
この本で紹介されている自然環境教育や音楽教育といった領域ごとの実践例は、あなたの園でも取り入れられるヒントの宝庫です。
【実践のポイントを抽出する】
例えば、音楽教育の事例から、技術を教えるより、音を感じてイメージする力(音感受)を育てるという視点を学んだとします。
実践では、普段の歌遊びで「どんな音が聞こえる?」「どんな気持ちになった?」といった問いかけを増やすなど、今の保育に少しだけ新しい視点を取り入れてみることから始めましょう。
まとめ
『子どもが中心の「共主体」の保育へ』は、主体性という言葉の重荷からあなたを解放してくれる、まさにアップデートのための一冊です。
自由保育と一斉保育のどちらかを選ぶのではなく、両方の良いところを認め合い、子どもと大人が共に成長し合う共主体という考え方を手に入れることで、あなたの保育への悩みはきっと軽くなります。
ぜひこの本を読み、あなたらしいバランスの取れた保育を見つけてください。