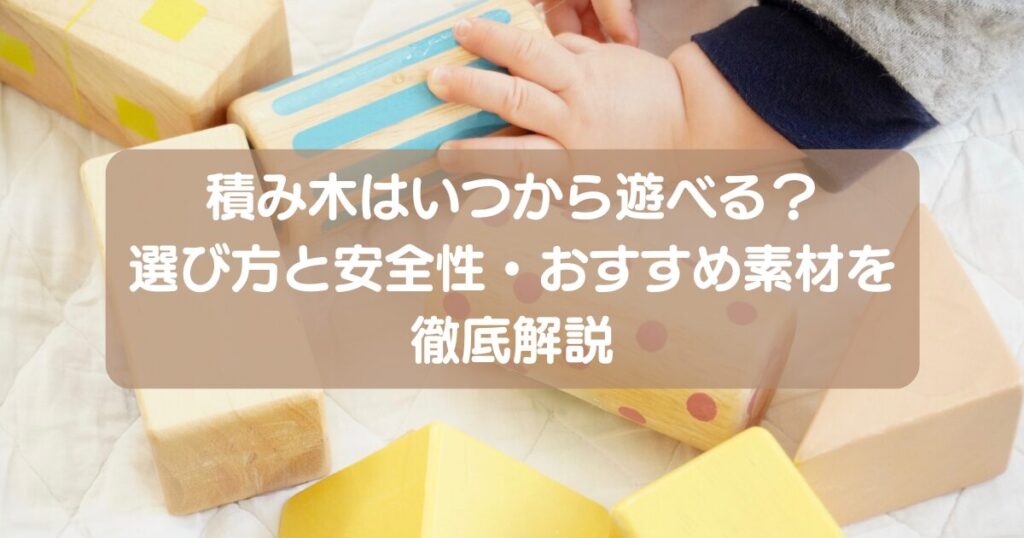積み木は昔からある定番のおもちゃですが、実は「どんな素材を選ぶか」「どんなサイズが良いか」で遊びやすさも発達への効果も大きく変わります。
安全性や価格もさまざまなので、初めて購入する時には迷う方も多いのではないでしょうか?
この記事では、積み木で遊ぶメリットをはじめ、素材・カラー・サイズ・安全性の選び方をポイント別に詳しく解説します。
赤ちゃんから幼児期まで安心して遊べる積み木を選びたい方は、ぜひ参考にしてください。
積み木で遊ぶメリットとは?
積み木の購入を検討していますが、メリットはありますか?
積み木にはお子さんの発達を促すたくさんのメリットがありますよ!
ここから詳しくみていきましょう。
積み木遊びのメリットには、次の4つがあります。
【メリット】
- 積み木を掴んだり、積み上げたり、並べたりする動作で、手や指先の機能が発達する
- 崩さないよう慎重に積み上げることで、集中力が鍛えられる
- 物の大きさ、奥行き、高さ、位置関係などを立体的に理解でき、空間認識能力が高まる
- 完成をイメージながら遊ぶため、想像力や創造力が養われる
積み木は、子どものさまざまな力を育むのに適した遊びです。
成長後も生活の中で役立つ力を、遊びながら自然に身につけられるのは嬉しいですね!
素材で選ぶ|赤ちゃんから安心して遊べる積み木はある?


ここでは、素材別にみる積み木の選び方を解説します。
素材によっては赤ちゃんからでも十分遊べう上に、発達を促すメリットの多い積み木は、小さいうちから触れておけると良いですよ。
赤ちゃんにおすすめの素材
赤ちゃんには米粉製のものがおすすめです。
お米が原料のため、口に入れたり舐めたりする年齢でも安心して使えます。
【メリット】
- 軽くて丈夫にできている
- 角が丸くなっている商品が多く、ケガのリスクが少ない
【デメリット】
- 価格が高い
米粉製のものは食品由来で安全ですが、アレルギーがある場合には、事前に病院で相談してから購入を決める方が良いでしょう。
木製の積み木
木製の積み木は程よい重さがあるため、安定感があって積みやすいのが特徴。
木製の積み木は、ブナやヒノキで作られたものがほとんどです。
木のおもちゃならではの温かみも感じられますよ。
【メリット】
- 丈夫で長持ちする
- ブナ製は硬くて丈夫、多少雑に扱っても割れにくい
- ヒノキ製のものは、木製のなかでも軽く、手指がそれほど発達していない年齢の子どもでも遊べる
- 水に強い特性もある
【デメリット】
- 定期的なメンテナンスが必要
- カビが生えやすい
- 変色の可能性がある
カビや変色を防ぐため、使用した後はよく乾かして風通しの良いところに保管すると良いでしょう。
コルク製の積み木
コルク製の積み木は、柔らかく軽量な素材のため、ケガのリスクが少ないのが特徴です。
【メリット】
- 柔らかく軽量で、ぶつかってもケガをしにくい
- 倒れても衝撃音が小さい
- 落としても床を傷つけにくい
【デメリット】
- コルクのカスが出やすい
- 遊んだ後に掃除が必要になる場合がある
- 価格が高い
価格が高いのは難点ですが、食品衛生法の基準をクリアしているものもあり、安心して遊べるのが良いですね。
プラスチック・布製の積み木
プラスチックや布製の積み木は、水洗いできお手入れが簡単なのが特徴。
汚れてもすぐに洗えて清潔な状態を保ちやすく衛生的です。
【メリット】
- 木製などに比べて柔らかく、ケガのリスクが少ない
- 水洗いできるため、衛生的に保ちやすい
【デメリット】
- 布製の積み木は時間が経つと変形して積み上がらなくなる
- 直射日光、気圧の変化などによって変形や変色の可能性がある
子どもにはおもちゃの好みがあるので、お試しとして、安価なプラスチックや布製の積み木を与えてみるのも良いですね。
カラーで選ぶ|無塗装とカラータイプの違い


積み木には無塗装タイプとカラータイプの2タイプがあります。
それぞれのメリットをみていきましょう。
【無塗装タイプのメリット】
- 色にとらわれず、遊びの幅が広がる
- 子どもの想像力を育てられる
- シンプルで飽きにくい
【カラータイプのメリット】
- 好きな色を認識できるようになる
- 色の学習に使える
- 色彩感覚を養える
カラータイプなら、たくさんの色があるタイプがおすすめです。
色の種類が多いと子どもの想像力を促すきっかけになり、長く使えますよ。
無塗装タイプでもカラータイプでもメリットはあるので、年齢が低いうちはカラータイプ、年齢が上がってから無塗装を買い足すなど工夫すると遊びの幅が広がります。
サイズで選ぶ|年齢に合った基尺とは?


遊びやすい積み木を選ぶためには、年齢に合った基尺(きじゃく)のものを選ぶことが大事です。
基尺とは、積み木セットの基本となる寸法のこと。
積み木の中で最も小さい立方体の一辺の長さのことをいいます。
年齢に合った基尺の目安
| 0〜2歳 | 4〜5cm程度 |
| 2〜4歳 | 3.3〜4cm程度 |
| 5歳以上 | 2.5cm以上 |
特に0〜2歳ごろは積み木の選び方に注意が必要です。
一般的に、この年齢では3cm程度のおもちゃが口に入るとされています。
チャイルドマウス(乳児の口の大きさは直径32mm、3歳児は直径39mm)と呼ばれ、誤って飲み込んでしまう場合があるので大変危険です!
4cm以上ある積み木なら誤飲を防げるので、年齢の低いお子さん用に購入する場合はよく確認しましょう。
安全性で選ぶ|チェックしたい2つのポイント


長く使える積み木を選ぶには、安全性も大事です。
ここでは、チェックしたい2つのポイントを解説します。
面取り加工
積み木の尖った角を削り落とすことを「面取り」といい、次のようなメリット・デメリットがあります。
【メリット】
- ケガのリスクを減らせる
- 柔らかな印象のデザインになる
【デメリット】
- 積み上げたときに隙間ができる
積み木を選ぶときには、子どもの年齢や遊び方に合わせて、面取りの有無を選択するのが良いでしょう。
特に、赤ちゃんなど小さな子どもが遊ぶなら、面取りされているものがケガの心配が少なくおすすめです。
面取りなしのタイプでも、一般的には触ってケガをしないように角は加工されています。
ただし、価格が安い場合は、面取りがされていないことも!
購入前にカットしたままか最低ヤスリがけはされているかは確認した方が良いでしょう。
STマークの有無
STマークは、安全基準適合検査に合格したおもちゃにつけられるマークのことです。
日本玩具協会が定める安全基準(ST基準)があり、基準をクリアしたおもちゃには、STマークがつけられています。
STマークがついたおもちゃは、次の3つの検査項目をクリアしています。
1.機械的および物理的特性の検査
おもちゃの先端が尖っていないか?喉に詰まらせる大きさではないか?
2.可燃性の検査
燃えやすい素材が使われていないか?
3.化学的特性の検査
鉛や水銀などの有害物質が使用されていないか?
ケガの危険性や、有害物質が含まれていないかを細かく検査しているため、STマークがついている積み木は安心・安全で小さな子どもが遊ぶのにぴったりです。
まとめ
積み木は、手指の発達や集中力、想像力など、子どもの成長に欠かせない力を遊びの中で自然に育んでくれるおもちゃです。
選ぶときは 素材・カラー・サイズ・安全性 の4つを意識すると、年齢や発達に合ったものを選びやすくなります。
特に小さいうちは安全面を重視し、誤飲の心配がないサイズや、角の処理がきちんとされているものを選ぶと安心!
成長に合わせて買い足したり、カラーや素材を変えてみたりすると、長く遊べるおもちゃとして大活躍しますよ。
お気に入りの積み木を見つけて、親子でたくさん遊びながら成長を楽しんでいきましょう。