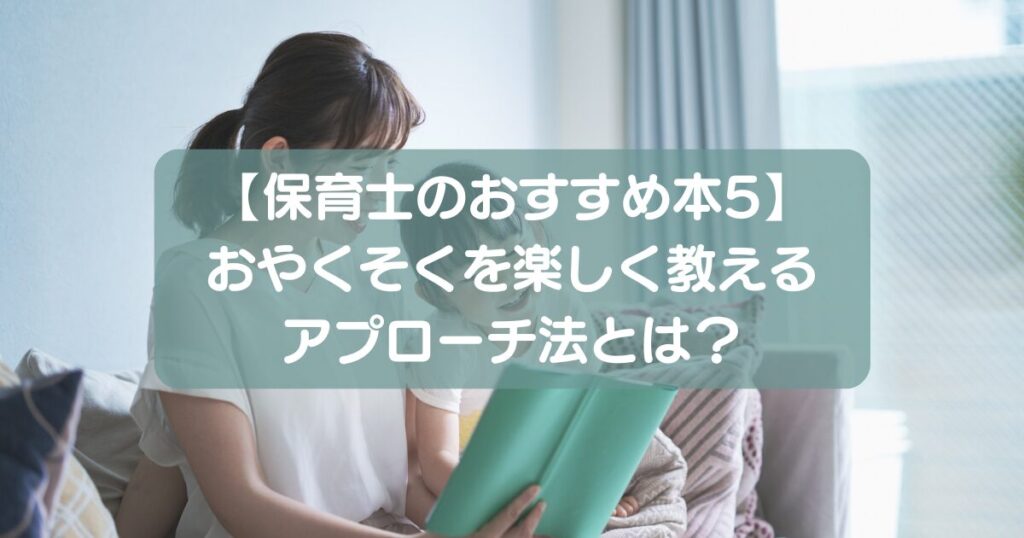「なんで順番を守ってくれないんだろう…」「ダメ!と言っても、なかなか伝わらない…」
毎日、子どもたちと向き合う中で、そう感じることはありませんか?
集団生活を送る保育園では、お片付けや順番を待つことなど、さまざまな「おやくそく」を子どもたちに伝える必要があります。
しかし、大人が一方的に「ダメ!」と叱るだけでは、子どもたちはなぜルールが必要なのかを理解できず、反発してしまいがち。
この記事では、子どもを伸ばす教育で知られる高濱正伸氏の著書『おやくそくえほん はじめての「よのなかルールブック」』を参考に、子どもたちが納得して「おやくそく」を身につけられる魔法のようなアプローチをご紹介します。
子どもが納得する!おやくそくの教え方
この本が画期的なのは、子どもたちが「なぜ?」と思うような日常のルールを、単純な「ダメ!」で終わらせず、理由を丁寧に教えてくれる点です。
例えば、「使ったものは元の場所に戻そうね」というルール。
子どもにとって「なぜ今すぐ片付けるの?」という疑問が生まれるかもしれません。
この本では、疑問に対し、「後でと思っていると忘れてしまうことがあるからだよ」「次に使うときに探す必要がなくなるし、部屋も気持ちよく過ごせるよ」といったように、子どもの目線に立ってわかりやすく解説しています。
また、すべてのページが絵本仕立てになっており、子どもたちと一緒に読み進められるのが大きな特徴です。
ルールをただ教えるだけでなく、絵本の世界を通して共感したり、話し合ったりすることで、子どもたちは自然とよのなかルールを理解し、身につけることができます。
「何かしてもらったら、ありがとうという」「せきやくしゃみをするときは、手やハンカチで口をふさぐ」といった小学校入学前後に身につけたい42の習慣を、子どもが楽しめる形で紹介していてわかりやすいです。
家庭でのしつけの仕方として書かれた本ですが、保育の中でも十分使えますよ。
子どもが楽しめる!「おやくそくえほん」の使い方

ここでは、日々の保育で「おやくそく」の伝え方をどう活かせるか、具体的なヒントを提案します。
理由を具体的に伝える「○○すると、こうなるよ」
ただ「〇〇しなさい」と指示するのではなく、その行動が周りにどんな影響を与えるかを具体的に伝えましょう。
「走らない!」
「ここで走ると、お友達とぶつかって痛い思いをしちゃうかもしれないよ」
この伝え方によって、子どもは自分の行動が他者とどう繋がっているのかを理解し、予測する力を育むことができます。
「よのなかルール」を絵本で共有する
子どもたちに集団でルールを伝えたい時、口頭で説明するのではなく、本書を読み聞かせに取り入れてみましょう。
「いやなことは相手に伝える」
絵本の主人公がいやなことを「いやだ」と伝え、お友だちに自分の気持ちを言葉で伝えようとする様子を一緒に体験する
絵本を通してルールを共有することで、子どもたちは自分と重ね合わせながら、共感的にルールを学ぶことができます。
本のチェックリストで「できた!」を見える化する
この本には、子どもたちが「おやくそく」を楽しく守れるように、「できた!」がわかるチェックリストが掲載されているのが大きな特徴です。
「これをしなさい」という一方的な指示ではなく、「〜しよう」と前向きな気持ちを引き出し、行動できたらチェックをつけるように促しましょう。
例:お片付けのルール
「使ったおもちゃを元に戻そう!」と伝えた後、「片付けられたらチェックをつけていいよ」と促す
子どもが自分から進んで行動する習慣を身につけるのに役立ち、自信とやる気を引き出すことができます。
まとめ
『おやくそくえほん はじめての「よのなかルールブック」』は、子どもたちが納得してルールを身につけるための、保育者にとって心強い味方となる一冊です。
絵本という親しみやすい形で、抽象的なルールを具体的な行動に落とし込み、その理由を丁寧に伝えることで、子どもたちは無理なく社会性を育むことができます。
この本を読み聞かせたり、日々の言葉かけに取り入れたりすることで、子どもたちの「なぜ?」に応え、自ら考えて行動する力を引き出してあげてください。