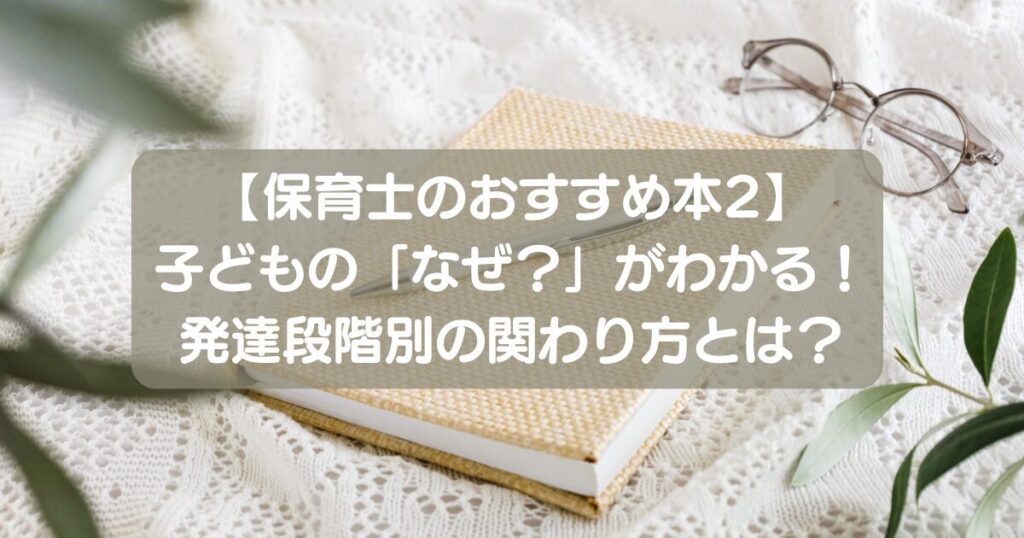「この時期の子どもって、どうしてこういう行動をとるんだろう?」「年齢によって、遊び方や言葉のかけ方を変えるべき?」
毎日の保育の中で、ふと疑問に思うことはありませんか?
子どもの行動一つひとつには、その年齢ならではの心と体の発達が隠されています。
その発達の道筋を理解することは、子ども一人ひとりに寄り添った質の高い保育につながります。
この記事では、金子龍太郎氏、吾田富士子氏が監修された『保育に役立つ!子どもの発達がわかる本』を参考に、子どもの発達を理解するヒントと、明日からすぐに使える具体的なかかわり方をご紹介します。
保育士必見!子どもの発達段階別の関わり方とは?
この本は、0歳から6歳までの子どもの心と体の発達を、豊富なイラストと図解でわかりやすく解説しています。
専門的な知識がなくても、子どもの成長の全体像を見える化してくれるのが最大の魅力。
特に注目すべきは、以下の3つのポイントです。
発達の「なぜ?」がわかる
子どもが泣き止まない時、友達とのおもちゃの取り合いが絶えない時…。
一見困った行動に見えるものも、実はその時期に特有の発達段階にあることがわかります。
その背景を知ることで、子どもへの理解が深まり、戸惑うことなく向き合えるようになります。
発達を促す「遊び」のヒント
年齢ごとの発達段階に合わせた遊びや玩具のアイデアが具体的に紹介されています。
例えば、0〜1歳児には指先を使った「つまむ・落とす」遊び、3歳児には「ごっこ遊び」など、その時期に伸びる能力を効果的に育むヒントが満載です。
「困った」を解決するアドバイス
子どもの発達に関してよくある悩みや疑問に対し、具体的なアドバイスが掲載されています。
発達の観点から、どう対応すればいいのか、どんな言葉をかければいいのかがわかり、日々の保育の「困った」を解決する心強い味方になります。
発達段階別に使える!保育士の関わり方3選

この本で得た知識を、実際の保育現場でどう活かせるのか、年齢別の具体例を見ていきましょう。
ほんの少し意識するだけで、子どもたちとの毎日がもっと楽しく、深い学びのある時間になりますよ。
0〜1歳:安心感の土台を築く「応答的なかかわり」
この時期の子どもは、周囲の人との信頼関係を築くことが最も重要です。
- 泣いたらすぐに抱きしめる
「泣くのはいけないこと」と叱るのではなく、「どうしたの?」と優しく声をかけ、抱きしめて安心させてあげましょう。 - 五感をフル活用した遊び
音の出るおもちゃを振ったり、布の感触を楽しんだり、五感を刺激する遊びを通して、新しい世界を体験させてあげましょう。
2〜3歳:「自分でやりたい!」を応援する
「イヤイヤ期」と呼ばれるこの時期は、子どもの自立心が芽生える大切な時です。
- 選択肢を提示する
「どっちの服がいいかな?」「どの絵本を読みたい?」のように、子どもに自分で選ばせる機会を与えることで、自己決定の力を育みます。 - 「できた」を具体的に認める
「靴下、一人で履けたね!すごい!」のように、できたことを具体的に言葉にして褒めることで、自信につながります。
4〜5歳:社会性を育む「対話」
友だちとの関わりが増え、ルールや相手の気持ちを理解し始める時期です。
- 言葉で気持ちを表現する手助け
「〜したかったんだね」「〜されると嫌な気持ちになるよね」と子どもの気持ちを代弁し、言葉で表現する手助けをしましょう。 - 遊びのルールを一緒に考える
遊びの中でトラブルが起きたとき、「どうしたらみんなが楽しく遊べるかな?」と問いかけ、子どもたちと一緒に解決策を考えることで、協調性や問題解決能力が育ちます。
まとめ
『保育に役立つ!子どもの発達がわかる本』は、子どもの行動に隠された発達のヒントを、保育者目線でわかりやすく教えてくれる一冊。
「わかっているつもりだった」ことが、改めて整理され、日々の保育がより意図的で深いものに変わるはずです。
子どもの発達という視点を持つことは、保育の引き出しを増やし、子どもたち一人ひとりの可能性を最大限に引き出すことにつながります。
この本を片手に、あなたの保育をさらに豊かにしていきませんか?