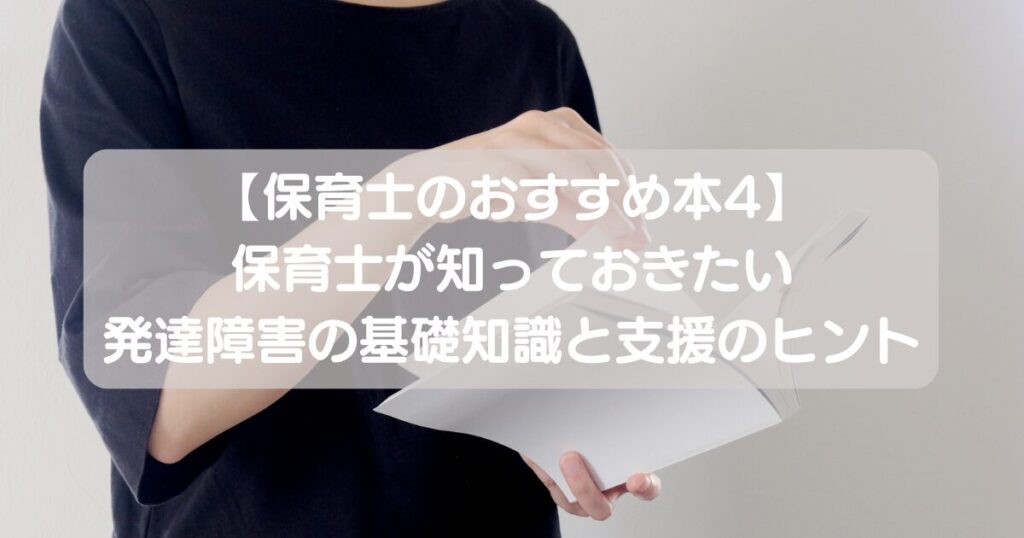「どうしてこの子は、みんなと同じように行動できないんだろう?」「特定のことにだけ、強いこだわりがあるのはなぜ?」
日々の保育の中で、子どもの行動に戸惑うことはありませんか?
発達に特性のある子どもたちの行動は、一見すると理解しにくいものかもしれません。
しかし、その背景にある発達の特性を理解すれば、子どもへの見方や関わり方が大きく変わります。
この記事では、田中康雄氏が監修した『発達障害の子どもの心と行動がわかる本』を参考に、発達障害の基礎知識と、保育現場で役立つヒントをご紹介します。
この本は、イラストと図解が豊富で、専門的な内容も視覚的にわかりやすく解説されており、発達障害について初めて学ぶ人にも最適な一冊です。
知っておきたい!発達障害の基礎から支援まで
この本は、自閉症スペクトラム(ASD)、注意欠如・多動性障害(ADHD)、学習障害(LD)など、発達障害の基本的な知識を網羅しています。
専門的な内容でありながら、難しい言葉を使わず、誰にでもわかるように書かれている点が大きな魅力です。
まず、「もしかして?」と感じた時のサインとして、保育現場でよく見られる気になる行動が具体的な例とともに紹介されています。
- 人と目を合わせない、名前を呼んでも振り返らない
- うまく気持ちが切り替えられない
- 集中できない、じっとしているのが苦手 など
上記のような、日常的な行動から読み取れるヒントが多数挙げられています。
また、「どうすればいいの?」という悩みに寄り添う内容も充実。
- 相談先がわかる
どこに相談すればいいのか、診断されたらどうすればいいのかなど、迷った時に役立つ情報が詳しく解説されています。 - 特性ごとの理解が深まる
自閉症スペクトラム、ADHD、LDそれぞれの特徴や、彼らが世界をどう見ているかが、イラスト付きでわかりやすく解説されています。これにより、子どもたちの行動が「なぜ?」から「なるほど!」に変わります。 - 多様な支援方法を知る
療育や薬の利用、そして家庭や保育園・幼稚園での具体的な支援方法についても触れており、子どもを多角的にサポートするための知識が得られます。
保育士必見!明日からできる保育現場での4つの支援例

この本で学んだことを、保育園や幼稚園、学校などの集団生活の場でどのように活かせるのか、すぐに取り組める支援のヒントを4つご紹介します。
この他にも、たくさんの支援のヒントが掲載されています。
ぜひ、本を手に取って現場で活かす参考にしてくださいね。
見通しを持てる環境づくり
ホワイトボードにその日の活動をイラストで示したり、写真付きのスケジュール表を活用したりすると、子どもは安心して活動に参加できます。
急な変更がある場合は、事前に伝える時間を確保しましょう。
「できる」を増やすスモールステップ
いきなり大きな目標を提示するのではなく、一つひとつの行動を細かく分解して、少しずつクリアできるような声かけをしましょう。
小さな達成感を積み重ねることで、自己肯定感が育ち、次の行動への意欲につながります。
得意なこと・好きなことを活かす
子どもが強い興味を持つことや、得意なことを遊びや活動に取り入れましょう。
例えば、電車が好きなら電車の絵本を読んだり、パズルが得意ならパズル遊びを促したりすることで、子どもの自信を育みます。
感覚への配慮
特定の音や光、肌触りなどを苦手とする子どもがいます。
大きな声で指示を出したり、蛍光灯の光が直接当たったりするのを避け、落ち着ける空間や物を準備するなど、感覚への配慮を意識しましょう。
まとめ
『発達障害の子どもの心と行動がわかる本』は、発達障害の基礎知識を、専門家ではない私たちにもわかりやすく伝えてくれる素晴らしい一冊です。
この本を通して、子どもたちの行動が「なぜ?」から「なるほど!」に変わり、一人ひとりの個性を尊重した、より温かい保育を実践するきっかけになります。
あなたの少しの理解と工夫で、子どもたちの成長を大きく後押ししていきましょう。