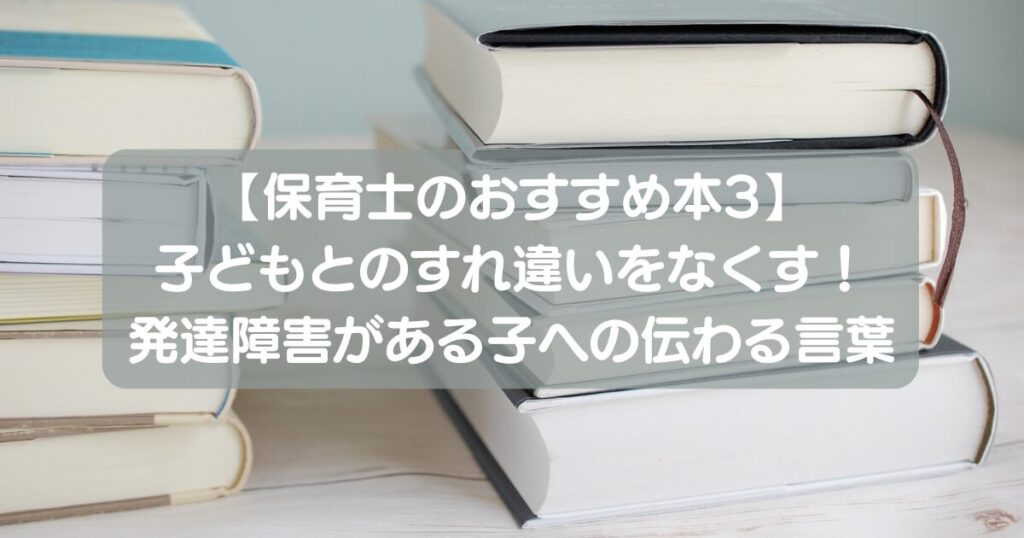「何度言っても、なかなか聞いてくれない…」 「どうして私の言葉は伝わらないんだろう…」と悩んでいませんか?
子どもたち一人ひとりの個性が光る保育現場では、言葉掛け一つで、子どもとの関係性や保育の質が大きく変わります。
特に、発達に特性のある子どもたち(「気になる子」)への言葉掛けは、より一層の工夫が求められます。
この記事では、守巧(もり たくみ)氏の著書『気になる子の保育「伝わる言葉」「伝わらない言葉」』を参考に、子どもに確実に届く「伝わる言葉」のヒントをご紹介します。
この本は、新人保育士さんだけでなく、ベテラン保育士さんにとっても、日々のコミュニケーションを見つめ直すきっかけとなる一冊です。
発達障害のある子への「伝わらない言葉」とは?
この本が教えてくれるのは、私たちがつい使ってしまいがちな「伝わらない言葉」の落とし穴です。
著者は、子どもたち、特に「気になる子」の特性を理解した上で、彼らが混乱してしまうような言葉かけを具体的に指摘しています。
- 曖昧で抽象的な言葉
「ちゃんとしようね」「しっかりやってね」といった言葉は、子どもにとって何をどうすればいいのかが不明確です。 - 否定や命令の言葉
「〇〇しないとダメ」「〜しなさい」といった命令形は、子どもの自発的な行動を妨げ、反発心を生みやすくなります。 - 複数の指示
「おもちゃを片付けてから、手を洗って、座ってね」のように、一度に多くの指示を出すと、子どもは混乱してしまいます。
これらの言葉がけは、悪意があるわけではありません。
しかし、子どもの特性を考慮すると、意図したように伝わらないことが多く、保育者と子どもの間にすれ違いを生む原因となります。
発達障害のある子に届く「伝わる言葉」3つのコツ

では、どうすれば言葉が子どもに「伝わる」ようになるのでしょうか?
この本では、明日からすぐに実践できる具体的なコツを、イラスト付きの事例でわかりやすく解説しています。
また、「気になる子」への対応に特化しつつも、言葉かけの方法はクラス全体の子どもたち、そして保護者や職員、専門職とのコミュニケーションにも応用できるのもこの本の特徴の一つ。
それぞれの場面での「伝わる言葉」「伝わらない言葉」の具体例が豊富に載っており、保育現場でのさまざまな人間関係を円滑にするヒントが見つかります。
具体的にシンプルに伝える
指示を出すときは、「何を」「どうすればいいか」を具体的に伝えましょう。
「ちゃんとお片付けしようね」
「赤い箱にブロックを入れてくれるかな?」
「静かにしてね」
「お口をチャックして、お耳でお話を聞いてね」
視覚的なヒント(指差しやジェスチャー)を加えたり、一つずつ段階を追って伝えたりすることで、子どもは次の行動を予測しやすくなります。
ポジティブな言葉で肯定的に伝える
否定的な言葉ではなく、子どもが「できること」「してほしいこと」を肯定的に伝えましょう。
「走らない!」
「歩こうね」
「おもちゃを投げないで!」
「おもちゃは優しく置いてあげようね」
肯定的な言葉は、子どもを安心させ、自尊心を育みます。
「〜しない」という禁止の言葉を「〜する」という行動の促しに変えるのがポイントです。
「〇〇しよう」「〇〇しません」の言葉掛け
発達に特性のある子どもは、相手の気持ちを推し量ることや言葉だけで真意を読み取るのが苦手な場合があります。
そのため、「〜されると私は悲しいな」というI(=私)メッセージだけでは、なぜその行動が良くないのかを理解するのが難しいことがあります。
この本では、代わりに具体的な行動を促す言葉掛けを推奨しています。
「どうしてバカって言ったの?自分が言われたら嫌でしょ?」
「その言葉は使いません」
「(高いところに登ったら)危ないよ」
「降りましょう」
問題行動の背景にある子どもの「〜したい」という気持ちに寄り添いながら、次に取るべき正しい行動を具体的に提示します。
正しい行動がわかると、子どもは「どうすればいいのか」を学び、自ら行動できるようになります。
子どもとのすれ違いをなくす!伝え方のポイント3つ

この本では、言葉そのものだけでなく、「どう伝えるか」も重要だと解説しています。
伝え方のポイントは以下の3つ。
話し方を見直す
声の大きさをコントロールし、はっきりとした声で、ゆっくりと話すことを意識しましょう。
子どもが大きな声を出している時には、保育者はわざと小さな声を出してみるのも効果的です。
また、注意や集中が苦手な子に対しては、子どもが理解できるスピードで話すことが大切です。
子どもそれぞれの注意が続く長さを理解して、その中で伝えるようにしましょう。
言葉かけを意識する
「しっかり」「ちゃんと」「丁寧に」といった曖昧な言葉は、気になる子にとって抽象的で苦手な言葉で、具体的なイメージがつきにくい場合があります。
「これ・それ・あれ・どれ・ここ・そこ」といった指示代名詞も苦手です。
伝える場合は短く、簡潔に、最後までハッキリと伝えることが重要です。
また、一文が長いと最後の言葉のみを切り取って理解してしまうので、一文を短く一つの行動が終わってから次の指示を出すと良いでしょう。
メリハリのある表情で
気になる子は人の表情から気持ちを察することが苦手な子がいます。
言葉の内容に合わせた表情をすることで、より気持ちが伝わりやすくなります。
大袈裟なくらい表情豊かに話すと良いですよ。
まとめ
『気になる子の保育「伝わる言葉」「伝わらない言葉」』は、専門的な知識がなくても、子どもの特性を理解し、より良いコミュニケーションを築くためのヒントが詰まった一冊です。
「伝わらない言葉」に気づき、「伝わる言葉」を意識して使うだけで、子どもたちの反応はきっと変わります。
そして、あなたの保育への自信とやりがいにつながるでしょう。
言葉一つで、子どもとの関係性は大きく変わります。
この本を参考に、明日からの保育が充実したものになることを願っています。