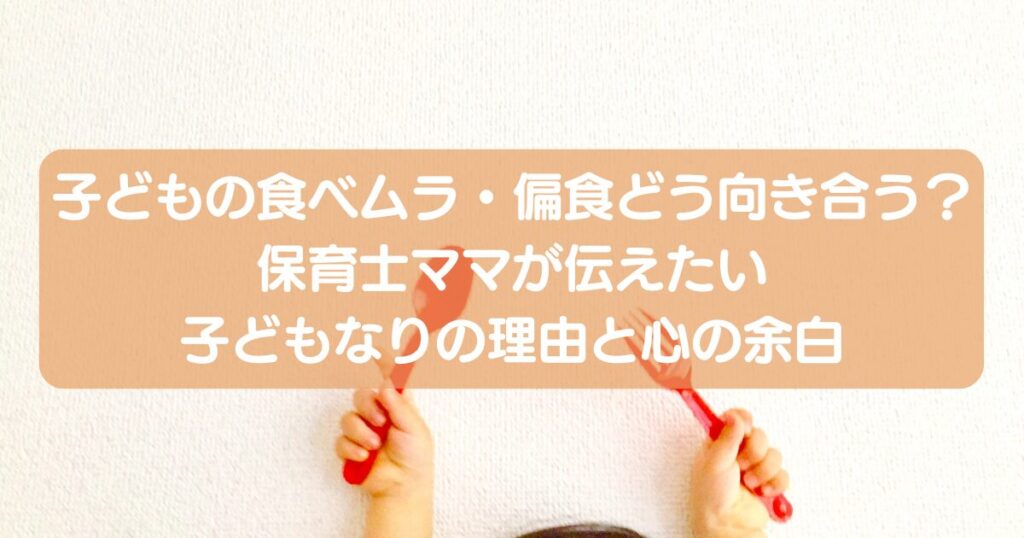「また食べてくれなかった…」「せっかく作ったのに、一口も食べない…」
子育てをしていると、子どもの食べムラや偏食に悩むことは誰しも一度はあるのではないでしょうか?
私自身、保育士として多くの子どもたちと関わってきましたが、食べムラや偏食のない子の方が少ないくらいです。
そして自分の子どもとなると、なおさら気になってしまうもの。
我が家の子どもも、1歳を過ぎた頃から急に食べるものが偏り始め、野菜や肉はほとんど拒否。
「どうして食べてくれないの?」と毎日のように悩みました。
でも、その経験を通して気づいたのは、子どもには子どもなりの「食べない理由」がちゃんとあるということ。
この記事では、保育士・母親という2つの視点から、子どもの食べムラ・偏食への理解と、親の心が少し楽になるヒントをお伝えします。
食べムラと偏食は別物?まずは違いを知ることから
子どもがご飯を食べてくれなくて悩んでいます…。
お子さんが食べてくれないと心配になりますよね。
ここでは、まず今の状態が食べムラなのか偏食なのかみていきましょう!
「昨日は食べたのに、今日は全然…」「週末はもりもり食べたのに、平日はちょっとしか…」そんな波のある食べ方をしている子は、「食べムラ」の状態かもしれません。
- 食べムラ:体調や気分、環境によって食べたり食べなかったりの差がある状態。成長過程ではよく見られます。
- 偏食:特定の食材やグループ(野菜、肉など)を継続的に拒否する状態。感覚過敏やトラウマなどが背景にあることも。
どちらも珍しいことではなく、年齢や発達に応じて一時的に現れることがほとんど。
ただ、偏食は原因に気づかずに叱ったり無理に食べさせたりすると、子どもの食べることへのハードルをさらに高くしてしまうこともあります。
保育の現場でもよくみる食べムラ・偏食の理由5つ


保育園や幼稚園では、毎日の給食でいろんな子の「好き」「嫌い」と向き合います。
そこで見えてくるのは、「食べムラ・偏食=わがまま」ではなく、子どもなりの感覚や経験が影響しているということです。
感覚が敏感で、食べることが苦手
トロッとしたスープ、ヌルヌルしたオクラ、パサパサしたささみ。
大人にとっては些細なことでも、感覚が敏感な子にとっては気持ち悪いレベルの刺激になります。
これは運動や音に敏感な子がいるのと同じで、本人のせいではありません。
食べること自体がストレスになる子もいるという視点を持つだけで、対応の仕方が変わってきます。
食材の見た目や形への拒否感
緑の野菜、形の不ぞろいな食材、混ぜご飯…「なんだかわからない」は、子どもにとって恐怖。
特に初めての食材は、本能的に警戒してしまうのが普通です。
これは危険を避けるための防衛本能のひとつであり、決して気まぐれではありません。
過去のイヤな記憶が残っている
一度吐いた、喉に詰まりかけた、においで気分が悪くなった―そんな経験があると、その食材自体に「イヤなイメージ」が染みついてしまうことがあります。
保育の現場でも、「前に食べて泣いたから、今日はやめとこう」と話す子がいるほど。
食の記憶は意外と深く、思い出させないよう配慮することが大切です。
食への興味が薄い or 他に集中している
そもそも「食より遊び!」という子もいます。
食べることにあまり意識が向かず、空腹を感じにくい子もいて、こうしたタイプは食事の優先度が低い傾向にあります。
この場合は、まず食事の楽しさを伝えることから始めましょう。
食具が使いにくく食べたくない
スプーンやフォーク、箸がうまく使えず、こぼしてばかりだと「食べたくない!」という気持ちに。
これは子ども自身が失敗=嫌なことと感じているサインかもしれません。
保育士としても、「手づかみOK」「遊び感覚で食べていいよ」と伝えることで、少しずつ安心感を育てていきます。
家庭でできる無理なく試せる工夫


私自身も母として、「どうしたら食べてくれるんだろう」と日々頭を悩ませました。
保育士という仕事柄、子どもの食行動には理解があるつもりでも、我が子が食べない姿を前にすると焦りや不安は拭えないものです。
正解はありませんが、うちの子には合っていたやってよかったことを具体的にご紹介します。
無理に食べさせない|見るだけ・並べるだけでもOK
以前は、「せっかく作ったんだから一口でも…」とつい強引に口元へ運んでしまうことがありました。
でも、それでは子どもはますます「食べる=嫌なこと」と感じてしまいます。
そこで意識したのは、食べなくてもいいけど、テーブルに出す。
好きなメニューの隣にそっと並べておくだけの日もあります。
すると、ある日突然「これなに?」と聞いてくれたんです。
まずは「見ること」「匂いを感じること」から始めるのが、子どもにとって大事なステップだったんだと気づきました。
味つけを「いつもの味」に寄せてみる
苦手な野菜も、慣れた味付けなら少し安心できることもあります。
例えば…
- 野菜はそのままだと食べないけれど、ケチャップ味なら食べる
- チーズ風味のグラタンに混ぜ込むとパクパク食べる
- ポテトサラダは無理でも、フライドポテトにすればOK
うちの子は「これカレー味だよ」と言っただけで、なぜか構えずに口に運んでくれたことも。
子どもにとって味の安心感は大きな武器です。
選ぶ・触るは食べる一歩手前
「何を食べるか自分で選ぶ」だけでも、子どもの食への関心は高まります。
スーパーでは、「このにんじん細いね」「今日はどれが美味しそう?」と、野菜売り場で声をかけます。
触って、選んで、袋に入れる。
自分が選んだ=自分ごとになるんですね。
家でも、簡単なお手伝い(混ぜる・型抜きする・盛り付ける)をお願いするだけで、驚くほど食いつきが変わります。
「これ、わたしが作ったんだよ」とニコニコで食べてくれた日は、親の私もうれしくてたまりませんでした。
見た目の演出は子どもにとって「ワクワクする入口」
子どもは「おいしそう」よりも、「楽しそう」で食いつきます。
- 型抜きで星やハートのにんじんにする
- キャラクターのピックをさす
- おにぎりを顔つきにして「今日は誰おにぎりかな?」と話題にする
- 色のバランスを整えてカラフルお弁当風にするだけで気分UP
例えば、にんじんが苦手だった我が子も、アンパンマンの型で抜いただけで食べてくれたことがあります。
子どもにとって「食べる」=「遊びの延長」であっていいんです。
できたことを見つけて声をかける
「食べなかった=ダメ」ではなく、「見てくれた」「においをかいでみた」だけでもOKと捉えるようにしました。
「今日は手でちょんって触ったね」
「前より近くに置けたね」
「におい、平気だったって言ってたよね」
そんなふうに、評価のハードルを下げる声かけを続けていくと、本人も「失敗じゃない」と思えるのか、少しずつ食卓での様子が変わっていきました。
保育士視点で大切にしたいその子なりのペース
保育園でも、無理に食べさせることはありません。
まずは「楽しく座っていられる」「見慣れる」「食べ物に親しむ」だけでも十分な成長と考えます。
特に、偏食が強い子は「何をどこまでできたか」に焦点を当てることで、保護者の方の気持ちも軽くなり、関係性がよくなる傾向にあります。
家庭でも、できないことよりできたことに目を向けてみてください。
食べムラ・偏食があっても大丈夫!育つ力はちゃんとある


子どもが何も食べてくれないと、自分を責めたり焦ったりしてしまいます。
でも、保育士として多くの子を見てきたからこそ言えるのは、「食べムラ・偏食があっても、子どもはちゃんと育つ」ということ。
実際、小学校に上がる頃には驚くほど食べられるものが増える子もいます。
味覚も感覚も、経験とともにゆっくり育っていくもの。
今できることは、焦らず・比べず・怒らず、見守る姿勢を持つことです。
そして何より、あなたが毎日悩みながらも工夫をしていることこそが、子どもにとって一番の栄養になっているのだと思います。
まとめ
「ちゃんと食べさせなきゃ」「偏食を直さなきゃ」と、自分を追い込んでしまうママは、本当に頑張っている証拠です。
でも、今日食べられなかったって大丈夫!
栄養バランスも、発達の個性も、すぐに整わなくていいんです。
食べてくれないではなく、食べられる日を待とうと思えたら、それだけでずいぶん心が楽になります。
あなたの悩みは、あなたが子どもを大切にしている証です。
それを、どうか誇りに思ってくださいね。