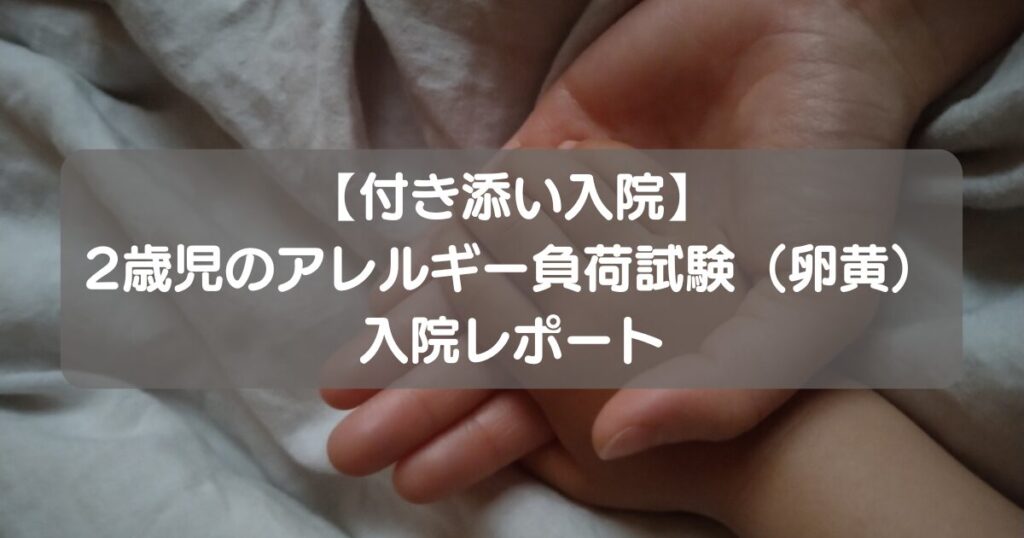「負荷試験」と聞くと、どんな検査なんだろう?付き添い入院ってどんな感じ?何を持っていけばいいの?と不安でいっぱいになりますよね。
私の2歳の子どもは、卵黄による消化管アレルギーあり、大学病院で2泊3日の入院を伴う負荷試験を受けました。
結果的に風邪による発熱で途中中止にはなったものの、この入院を通して、親として知っておいてよかったこと、あらかじめ準備すべきことがたくさん見えてきました。
この記事では、入院負荷試験の流れや実際の持ち物、病室での過ごし方、親の食事や寝泊まりの工夫まで、リアルな体験をもとにまとめています。
すべてのご家庭が同じ流れになるとは限りませんが、これから負荷試験に臨むお子さんとご家族の「少しでも心の準備」ができるよう、私の体験がお役に立てたらうれしいです。
【付き添い入院】何のアレルギーで入院したの?
付き添い入院って何をするんですか?
初めて付き添い入院をするとなると、不安なことが多いですよね。
私は子どものアレルギー負荷試験のために付き添い入院を経験しました。
ここからは、我が子の入院の様子を詳しくお伝えしていきます。
まず、私の子どものアレルギーは食物蛋白誘発胃腸症というものです。
これは、特定の食品を食べた後に少し時間を空けてから、嘔吐や下痢、ぐったりするなどの症状を引き起こすアレルギーの一種。
消化管アレルギーといわれることもあり、我が子は卵黄が原因でした。
食物蛋白誘発胃腸症は、血液検査ではアレルギー反応はでないのに、特定の食品を食べると嘔吐や下痢といった症状が見られるため、実際に食べてみないとアレルギーがなくなったかどうかわかりません。
我が子は離乳食中期ごろに卵黄を食べて数時間後に大量嘔吐したことが2回あったため、食物蛋白誘発胃腸症だと診断され、2〜3歳頃に経口負荷試験を行うとされていました。(このアレルギーは年齢が上がるにつれて自然に治っていることが多いそうです)
【付き添い入院】準備と心づもりは?


入院を伴う負荷試験と聞いて、まず気になったのは「何を持っていけばいいのか」「どう過ごすのか」でした。
特に付き添い入院の場合、子どもだけでなく親の生活もまるごと病院に持ち込むことになります。
ここでは、実際に入院してみて「これは準備してよかった」「持っていけばよかった」と感じたものを中心に、入院前に知っておきたいポイントをまとめました。
事前に確認しておきたいこと
1.病室のタイプは?
個室か大部屋かは、希望できても確実ではない場合が多いです。
環境が変わる可能性もあると知っておくだけで、心の余裕が違います。
我が子が入院した病院はお部屋の希望は全くできませんでした。
2.設備はどこまで使える?
冷蔵庫・テレビ・Wi-Fiなどが有料の病院も。
あらかじめ確認しておくと便利です。
我が子の病院は、冷蔵庫・テレビ・Wi-Fiの利用は有料でした。
また、入院セット(バスタオル、フェイスタオル、子ども用のパジャマ、BOXティッシュ、コップ、歯ブラシセットorお尻拭き)も有料でしたが、タオルは荷物になるので借りました。
3.プレイルームの有無・利用は?
医師の許可が必要な場合があります。
自由に遊べるとは限らないことも頭に入れておきましょう。
入院した病院は小児病棟にプレイルームがありましたが、一家庭ずつ1回15分以内と決まっていました。
我が子は食べたあと数時間後に嘔吐があるアレルギーだったので、体を使って遊んでしまうことによる誘発を避けるために午前中は利用しないように言われていました。
入院に持って行ってよかったもの
2泊3日の短期入院とはいえ、慣れない環境で過ごす2歳児にとっては大きなストレス。
快適に過ごせるよう、できるだけいつもの環境を再現できるものを意識して持って行きました。
子ども用
- ガーゼケット(お昼寝や就寝時に安心できた)
- 絵本やお気に入りのおもちゃ(大部屋なら音が出るものは避けましょう)
- スマホで動画を見る用のアプリ(Amazonプライムなど、ただし大部屋は音ありNG)
- 寝る時のオルゴール音楽(いつも夜通しかけているのでスマホにダウンロードして持ち込みましたが、大部屋ならNGです)
- 好みの調味料(ふりかけなど、負荷試験に使える範囲で)
- 食事用エプロン、スプーン、フォーク、コップ(使い慣れているものがあると安心)
親用
- モバイルバッテリー、充電器(スマホの充電関係は必須です)
- 延長コード(病室によってコンセントの位置がわからないのであると便利)
- 小さめバッグ(買い物時などに便利)
持っていけばよかった、借りればよかったもの
・レジャーシート
床で遊ぶときの衛生対策にもあれば便利だったと感じました。
最初は個室だったので、子どもがベッドの上よりも靴、靴下を脱いで室内を歩き回って遊ぶ方がリラックスできたようです。
食事の際はハイチェアの貸し出しがありましたが、数に限りがあるため、ベッドの上で食事をとる際の食べこぼし用にもあると便利。
・冷蔵庫、テレビ、Wi-Fiの有料貸し出し
スマホでも動画は見られましたが、「おかあさんといっしょ」などはテレビでも見られるようにしておけばよかったなと思いました。
入院前の心づもり
• スケジュール通りに進まないこともある
今回は途中で子どもが発熱し、3日目の検査が中止になりました。
そうした想定外も含めて考えておくと、気持ちがラクになります。
• 付き添い親も「寝られない」「食べられない」前提で準備を
椅子での仮眠はつらく、ベッドで添い寝した方が子どもも安心して眠れました。
夜中に何度も起きることも想定して、できるだけ親の負担を減らす工夫が必要です。
• できれば、荷物は少し多めを意識して
現地で調達できないものも多く、院内のコンビニなどでは限られていることが多いです。
多めに持っていって困ることはありませんでした。
入院初日:卵黄2g摂取の日


入院初日は、午前中からさっそくスケジュールが詰まっているので、事前に流れを把握しておくとバタバタせず落ち着いて対応できます。
我が家のスケジュールは以下のような感じでした。
入院初日の流れ
1.診察予約時間(10時)までに入院手続き
2.小児科外来へ移動
・身体測定
・医師の診察(体調チェック)
・点滴のルート確保
3.負荷物質(卵黄2g)を摂取
・自宅で調理して持参(味付けにアンパンマンふりかけ)
4.病棟へ移動、経過観察
・小児科病棟へ移動
・書類の説明や記入、ベッドやプレイルームの使用説明を受ける
卵黄(アレルギー食材)の準備について
病院から「調理して持ち込んでください」と言われていたので、あらかじめ15分茹でた固茹で卵黄を丸々持っていきました。
外来で卵黄2g分を測ってもらい、子どもが食べ慣れた味(アンパンマンふりかけ)を少量かけて摂取。
好みに偏りがあるお子さんの場合は、「食べられそうな味付けの確認」を事前にしておくと安心です。
病棟・個室の様子と過ごし方
初日の病室はトイレ・洗面台付きの個室でした。
個室で過ごしてみて、良かった点や気になった点をいくつかお伝えします。
1.ベッドが高く、2歳の子には遊ばせるのは危険
親が目を離さないこと、床に座れるスペースを確保するのがおすすめ。
全面柵で囲えるタイプのベッドで、少しでも目を離す際には柵を1番上まで上げるよう説明がありました。
2.ハイチェアの貸し出しあり
食事の時間に空いていれば自由に借りられました。
ベッドの上での食事は難しそうだったので、食事がしやすくて便利でしたよ。
3.プレイルームあり
小児病棟には、1家庭15分ずつ使えるプレイルームがありました。
ただし、使用には医師の許可が必要で、症状次第では利用できない場合も。
食事と生活の工夫
入院初日は、夜ご飯から子どもの食事は出ますが、親のご飯タイミングが難しいです。
子どもは病棟外に出られないため、以下のような工夫をしました。
1.子どもが昼寝しているタイミングにコンビニへ買い出し
我が子は離れるとダメだったので昼寝か就寝後でないと買い物ができませんでした。
2.子どもが食べたがりそうなものは避ける
うどん・パンなど我が子の好物。
親のご飯は好物を避け、サラダとおにぎりなどで済ませました。
3.小児病棟内にある設備
電子レンジと自動販売機があり、電子レンジは親御さんが自身のご飯を温めるために結構使っていました。
ポットなど、お湯はなかったので味噌汁やカップ麺はコンビニでお湯を調達するしかなく、危ないので諦めました。
就寝までの工夫
慣れない環境での就寝は予想以上に時間がかかりました。
寝つきをよくするためにやってよかったこと
- ガーゼケットでいつものお昼寝感を出す
- 添い寝して落ち着くまでそばにいる
困ったこと
- 個室内は暗くできても病室のドアは勝手に閉められないので、ナースステーションの明かりが20時頃でも明るく、寝にくい
- ベッドの柵の音が大きく、寝返りでガシャガシャ音がして起きてしまう
- 入院している子どもの泣き声、ピーピーと機械音が鳴り続ける、話し声などが気になる
親は椅子で寝ようと思っていましたが、やはり無理で…ベッドの隙間に柵を上げて添い寝。
結果的に子どもも夜中に起きたとき、すぐトントンしてあげられてよかったです。
2日目:卵黄半分(約8g)摂取の日


2日目は、いよいよ負荷量が増える日。
初日は無事に過ごせたものの、やはり親としては「大丈夫かな…」と少し緊張しました。
この日は朝から病院でのルーティンが始まり、朝食時に卵黄の約半分(8g)を摂取。
子ども自身も1日目より環境に慣れた様子で、個室内で遊んだり窓から外を見たり、病棟内を歩きたがるなど余裕が見られました。
午前:負荷試験の2回目
・朝の診察、体調チェック
・調理済みの卵黄(約8g)を摂取
・経過観察は病室内で。特に症状は見られず、一安心。
食べた量は1日目より明らかに多く、見た目にも「こんなに大丈夫かな…」と不安になるくらいでしたが、子どもは特に嫌がることもなく完食。
摂取後も特に嘔吐や腹痛などの異常は見られませんでした。
午後:プレイルームと親子シャワー
午前中に問題がなかったので、医師の許可を得てプレイルームで少し遊びました。
おもちゃや絵本があり、久しぶりにのびのびと遊ぶ姿に少しホッとしました。
午後には親子でシャワーも使用可能に。
・点滴ルートはビニール袋で保護してもらえる
・使い方や注意点は看護師さんが丁寧に説明してくれた
普段どおりのスキンシップやケアができたことも、子どもにとって安心材料になったと思います。
夕方:突然の大部屋移動での戸惑い
午後のシャワー後、「今から大部屋へ移動してください」との急な連絡。
ベッドごと別の部屋に移動することになりました。
大がかりな移動に子どもは不安そうに泣いてしまい、音や気配に敏感な子には少しハードだと感じました。
夜:まさかの発熱
夜、急に子どもの体が熱くなり、検温すると39度台の発熱。
この日は検査自体に問題はなかったものの、風邪症状が出てしまったようでした。
たまたま、担当医が院内にいたため、すぐに診察をしていただき、解熱のため坐薬を使用することに。
3日目の負荷(全卵摂取)は中止の可能性が高いと伝えられ、夜だったこともあり、そのまま朝まで様子を見ることになりました。
大部屋での就寝でしたが、発熱によるだるさもあってか、子どもはスッと眠りについてくれて良かったです。
2日目を終えて感じたこと
負荷量が増えることで心配も増しますが、子どもの様子をよく観察すれば過剰に不安がらなくても大丈夫です。
ただし、今回の我が家のように急な対応を迫られることもあり、環境の変化(大部屋移動など)が、子どもにとって大きなストレスになる可能性は十分にあります。
付き添いの親も、気力・体力の余裕を持っておくことが大切です。
3日目:負荷検査中止と退院


本来ならこの日は負荷試験の最終日で、全卵(卵黄約16g+卵白)を摂取する予定でした。
ところが、前夜からの発熱が続き、朝の時点でも体温は下がらず…。
医師の判断により、負荷試験は中止、「半分までクリアしているので、全卵は元気になってから外来で行いましょう」と説明を受け、退院の方向となりました。
退院に向けた手続きと説明
- 全卵の外来負荷試験の日程を予約(約2ヶ月後)
- 試験内容や当日の持ち物、時間帯の説明
- 入院生活を振り返っての医師との面談
退院のタイミングは昼前ごろ。
この日は子どもがまだ発熱していたので、その足でかかりつけ医に直行しました。
結果はなんと…アデノウイルス。
保育園でも流行っていたようで、ここでようやく原因が判明しました。
今後の「外来での全卵負荷試験」について
退院時に、次回の試験の詳細を教えてもらいました。
【外来での負荷試験】
- 来院は朝9時ごろ
- 点滴のルート確保・身体測定・診察後に、持参した全卵を摂取
- 接種後は15時ごろまで病院内で様子見
- 摂取の3~4時間前から絶食(朝ごはんは早めに)
- 朝食後は水かお茶だけOK
- 昼食は控える
今回は入院付きだった負荷試験でしたが、全卵の外来試験は日帰りで済む予定とのことで、精神的にも少しラクになると感じました。
退院時に感じたこと
結果的に全卵までは試せなかったが、半分まで摂取できたこと自体が大きな前進で、「ここまでよく頑張った」と思える日になりました。
無理に続けて症状が出てしまうと、また半年〜1年はアレルギー対応になってしまうため、再入院を回避できたのは何よりも良かったです。
また、担当医も「体調不良で入院自体をキャンセルする場合も多くある」と言っていましたが、今回の我が家のように入院中に体調を崩すこともあると知っておくだけで、予定変更にも柔軟に対応できると思います。
退院した今は、次回の外来負荷試験に向けての準備も始めつつ、子どもと一緒に休息を取ってあげたい気持ちでいっぱいです。
付き添い入院では親の生活や負担も大きい


アレルギーの負荷試験というと、子どもの体調や検査の進み具合にばかり気が向きがちですが、実際に入院してみて思ったのは、親の付き添いも予想以上にハードだということ。
病室での過ごし方、食事、睡眠、気持ちの切り替えなど、実際に経験したからこそ見えてきた「リアル」をお伝えします。
付き添い中の「食事問題」
病棟から子どもが出られないため、親は子どもを一人にせずに食事をとる必要があるのがなかなか大変でした。
• 昼寝や就寝後を狙ってコンビニに買い出しし気分転換
冷蔵庫は借りていなかったので買いだめはせず、何度もコンビニに行きましたが、病室から出るだけでもちょっとした気分転換になりました。
• 寝ている時に食べる用として自分のちょっとしたお菓子も◎
子どもの好物や欲しがりそうなものは避け、サラダとおにぎり生活だったこともあり、子どもが寝ている間にささっと食べるお菓子でお腹を満たしました。
「睡眠」は想像以上にとれない
親の寝床は基本的に椅子か、子どものベッドの隙間。
子どもが小さい場合は全面柵付きのベッドになるため、寝ている間は柵を上まであげておかなければなりません。
親の寝具はもちろんないため、上着を持ち込んでかけて寝ましたが、冬など寒くなれば親用の寝具も持参した方がいいかもしれません。
心の負担と向き合い方
親としては、「今日どこまで進められるかな」「この量、大丈夫かな」と気を張り続ける数日間。
不安な顔は見せたくないけれど、緊張感は常にあります。
そんな中で私が意識していたことをまとめておきますね。
【入院中意識していたこと】
- 「検査が進むこと」だけが正解ではない子どもが元気で帰れることが一番!
- 病院スタッフにこまめに相談・報告する一人で抱えず、些細なことでも伝えておくことで心の余裕ができました。
- 完璧を求めすぎない睡眠不足・食事の乱れなど、親のコンディションが悪くなるのは当然。自分も労わってあげてよいと思います。
まとめ
アレルギーの負荷試験というのは、親にとっても子どもにとっても、決して軽くはない経験です。
不安も、緊張も、そして「ちゃんと進めるかな…」という焦りのような気持ちも、私自身がまさに感じたものでした。
この体験を通して強く感じたのは、負荷試験は無理に進めるものではなく、どんな結果であっても、子どもの体にとって一番安全な方法が選ばれるのが何よりもの安心材料であること。
準備することも、気をつけることもたくさんありますが、この記事が少しでも「負荷試験ってこういう流れなんだ」「これを持っていけばいいんだ」と感じてもらえる参考になれば嬉しいです。
不安や心配がゼロになることは難しいかもしれません。
それでも、「大丈夫、なんとかなる」と思える材料をひとつでも持って、親子で一歩ずつ進んでいけますように。